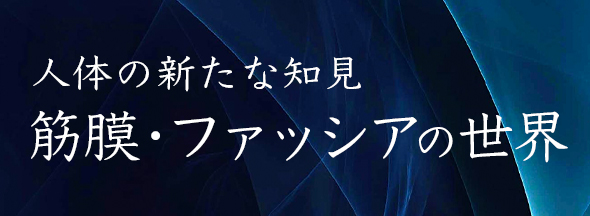第39回経絡治療学会学術大会 九州大会 レポート

第39回経絡治療学会学術大会九州大会が、令和7年3月29日、30日、アクロス福岡4F国際会議場にて開催され、約250人の参加者が福岡の地に集った。今大会は「経絡治療の診断と治療 ~六部定位脈診の捉え方~」をテーマに掲げ、九州では第29回大会以来の開催となった。本学会会長、岡田明三氏の体調不良により、副会長の今野正弘氏が代役を担い、大会会頭は馬場道敬氏、実行委員長は馬場道啓氏が務めた。
目次
開会式
馬場道啓氏の開会宣言にて幕を開け、馬場道敬氏の会頭挨拶では、鍼灸が中国から1500年前に伝来し、江戸時代までは医療の中心的な役割を果たしていたが、西洋文化が台頭したことによる西洋医学に代わっていった時代の中で、昭和14年に経絡治療という名の下に鍼灸が復興された歴史を辿り、学と術=学問と実技を両論に実践してきたこと、また臨床に重きを置いていること、さらに本大会のプログラム概要から鍼灸の本道である経絡治療の実態に接する機会と伝え、参加者へ謝辞を述べた。続く今野正弘氏は、壇上にて、経絡治療が産声を上げてから様々な物語が資料から伺うことができ、これまでの各世代に学術大会、夏期大学を通じて受け継がれてきていることは大変喜ばしいと述べ、11年ぶりに開催される福岡大会では十二分に満足いただける内容と信じているという言葉を贈った。
会頭講演「経絡治療の診断と治療」
馬場道敬氏は、はじめに柳谷素霊、竹山晋一郎、井上恵理、岡部素道らが経絡治療の普及に力を注いだ経緯から、新しいものに変わっていくものと変わってはならないものとの間で、どれほど歴史が古く、長くとも少しずつ変わっていくことが当たり前と前置きし、脈診については、脈の形よりも力が重要で、六部定位脈診を行う際は、指を直角に当て、術者の中指を患者の橈骨莖状突起に当てることを基準とするが、患者の腕の長さを考慮して行う。また、はじめは難しく考えずに六部それぞれの強弱を診て虚実を決定すると、指の当て方を見せた。具体的な証の症例として、目の充血、鼻血など出血を伴う症例は、腎経虚肺経実証で、症状がひどい場合は、水穴の尺沢よりも郄穴の孔最をとると指南。また、頭痛は腎経虚、肺経虚、胆経実証が多いと岡部素道の教えを交えながら解説した。さらに治療に関して、鍼は1寸3分、0~2番とし、刺入の深さは1~5mmと、灸は3~5壮と指定し、治療の質量を提示した。その他に、確実な取穴、また、即刺即抜、置鍼といった所要時間を考慮することが治療のコツとレクチャーした。

鍼灸院に来院する患者は様々で、それらに対応するためには左右の橈骨動脈拍動部を寸、関、尺の3部に分け、さらに浮沈で陰経、陽経に分けて計12経の虚実を診る六部定位脈診で証を決定。難経本義による選穴し、確実な取穴、鍼灸治療の質量の考慮、深鍼をせず、治療目標は、あくまでも経穴であり患部ではないと話す馬場氏
会長講演「腰痛の標治法と本治法」
岡田明三氏の代理として今野正弘氏が登壇。まず、初学者に向けて、脈診は重要だが難しいため、はじめは望診、聞診、問診、切診の四診で証決定することが大切と強調した。腰痛の原因について現代生活で考えられることは、冷たい物を好むといった食生活、外傷、年齢、大会当日が一変して冷え込んだことを話題に、気温の変動を例に挙げ、実技では徒手検査から始めて皮膚の状態を確認し、舌の色、形、動き、苔の色や質から臓腑の不調を判断する舌診を行った。腰痛の場合は、腰眼や痞根をチェックするが、今回のモデルのケースでは、腰にぷくっとした膨らみがあり、この部位に知熱灸をして血を動かすと教示した。

今野氏は、講演の最後に初学者に向けて、実際に治療を受けているかを問いかけ、治療を受けることで学んだことが膨らみ、フィードバックされるため、ぜひ経絡治療を受けていただきたいと参加者へ呼びかけた
特別講演「西洋医学的立場からみたプライマリーケア医(開業医)の現状について」
川元健二氏(かわもと胃腸内科クリニック院長)は、はじめに東洋医学について、自然治癒力を引き出すことで病気を根本的に治そうとする特徴から、病名がはっきりしない体調不良にも対応可能という長所がある反面、症状によっては治療期間を要し、ウィルス、細菌、毒にはアプローチしにくいといった短所を述べると、一方で、西洋医学の長所は対症療法で即効性のある治療を行うことができ、薬や手術で体の不調をすぐに改善できるが、病名がはっきりしない体調不良には効果的な治療が得られないといった欠点を示した。次に西洋医学における内科診断学の変遷、基本的アプローチを紹介。患者生命にかかわる危険なサインとして、意識状態、体温、脈拍などのバイタルサイン、心臓発作から脳卒中に関わる兆候を伝えると、現代医療には欠かせないものとして画像診断の重要性を説いた。画像診断の沿革において、1895年のレントゲン博士によるX線の発見を取り上げ、第一回ノーベル賞を受賞した初のレントゲン写真と実験室をスライド上で参照。画像診断技術の進歩を年表を用いて発表し、さらに腰椎椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症、腎癌、腹部大動脈瘤、胆嚢や総胆管結石などの診断画像をスクリーンにて供覧した。

患者が最初に相談し、初期評価や診断を行うプライマリーケア医としての役割を担う内科開業医の臨床現場の現状について講演した川元氏。根拠に基づいた医療が求められるようになり、現在の医療は画像診断なくしては成り立たないと伝え、より正確な画像診断が医療の質を保障する第一歩と展開した
実技公開「経絡治療の診断と治療 ~六部定位脈診の捉え方~」
実技をメインに講演を行った池田 政一氏(漢方池田塾主宰)。経絡治療において診察は最初に望診。次いで頭部、頸部、胸部、腹部、背部、患部などの切経で、同時に主訴に関連した問診および関連する事項の問診。最後に六部それぞれの脈状を診て、いずれかの臓腑経絡が虚または実になっているかを診る。虚実によって寒熱が発生するが、その寒熱がいずれの臓腑経絡に波及しているかを診察、問診して虚実、寒熱を決定し、証を決める。証の決定後、いずれの経絡、経穴を補瀉するかを決めて治療すると解説。実技中の脈診では、会場内から希望者を募り、壇上にて「指は乗せるだけ」「指を立てない」「指の先ではない」「ゆっくり沈める」と、直接指導する場面があった。主訴が立ちくらみの21歳男性には然谷と復溜を補い、寝つきの悪いという22歳男性には隠白から太谿を選穴した。

痛くない鍼である必要性を説き、まずは自分の足に刺し、痛いようであれば患者に行ってはならない。ただし、やさしい鍼では、患者にとって何を治療したか分かりづらいため、その場で行っている治療を説明しながら刺鍼するようアドバイス。さらに、「気」が分かるようになるまで修行を重ね、粗食、断酒、睡眠不足になってから勉強すると語り、脈に関して、少し分かるようになるまで3年はかかると伝えた池田氏
教育講演「日本の伝統鍼灸における経絡病証について」
和辻直氏(日本伝統鍼灸学会会長)は、日本の経絡病証の現状、経絡病証の必要性、日本の経絡病証の実際と今後の3つのテーマに関して、2022年1月に世界保健機構(WHO)が発効した国際疾病分類の第11版(ICD-11)との関連を含めて講演を行った。ICD-11の伝統医学章に鍼灸と関連が深い経脈病証があるが、伝統医学が国家の医療体制化にある中国や韓国と比べて、日本の現状はデータ集積できる環境を整備する段階にあり、その集積が鍼灸診療の有用性を示すために大きな意義を持つと提唱。鍼灸の貴重な医療資源の提示は、鍼灸師自身の課題であり、実現できれば、国民の健康に貢献し、医療費削減に寄与できると総括した。

今後、ICD-11のデータ集積の実施に向けて、日本の鍼灸学会、業団、教育関係などによる協力が不可欠で、集積したデータは診療報酬明細データ、疾患特異的患者登録。電子カルテデータなどリアルワールドデータに直結し、これを解析して得られた科学的根拠=リアルワールドエビデンスにつながる。これを国民への提示、還元する。そのためにデータ集積は急務と喚起した和辻氏
シンポジウム「六部定位脈診の現在」
六部定位脈診の捉え方や脈からどのような情報を得ているのか。師匠筋が異なる橋本厳氏、小泉智裕氏、山口誓己氏の3人をシンポジストに迎え、それぞれの講演の後、脈診実技、ディスカッションを行った。先陣を切った橋本氏は、冒頭で経絡治療の先陣と系譜を図で表し、人物とその関係性や歴史を分かりやすく視覚化。その中で、橋本氏が師事した岡田明祐の教えについて、脈診は、はじめに総按でじっくり診る。この時は基本的に黙って脈診を行い、次に単按で軽く診る際は症状を聞いたり世間話をしたりする。そして時々証名を言うといった手順について触れると、当時、脈を何度診ても分からず、その難しさに直面した頃に出会った首藤傳明著『経絡治療のすすめ』に助けられたといった経験を明かす一幕があった。小泉氏は、馬場白光に師事。眼精疲労の症例を基に、脈診は、脈状診ではなく左右寸関尺の浮沈中に部位での脈の強弱で十二経の虚実を診ると特徴づけ、必ずしも基本証によらず十二経の虚実を補瀉し、調えることで結果として証に辿り着くと論じた。山口氏は、大上勝行氏に師事。左右の手の寸口の脈を比較して、臓腑経絡の異常を判断する脈差診は、十二経の気の虚実を脈の虚実に置き換えて診ることで、変動を起こしている経絡を見つけることができ、病は経絡の変動と考えるため、六部定位脈診の要であると提言。脈差診に脈状診を加えて病理を明らかにしていくと脈診の特徴を図式化して分かりやすく表した。さらに証は肝虚証。沈実の刺鍼は速刺徐抜と進めた。

一般発表

「COVID-19の罹患後症状で脈沈細をあらわす症例」太田智一氏
慢性病でも同様に、商陽穴の刺絡が著効を示すほど陽経に実熱があっても、湿が絡むと沈細の脈を表す可能性があることが示唆されたと報告した。

「コロナワクチン接種後に増悪した腰下肢のしびれに対する経絡治療について」仙田昌子氏
患者が感じる鎮痛薬の効果が治療直後は向上したことから薬物療法と経絡治療との併用は、ペインコントロールに有用であると期待でき、痺れが発生した原因は明らかではないが、症状や罹患機関からも病因を見直す必要があったと発表した。

「『肺虚肝実証』を『肝虚寒証』で治療した調査報告」今野弘務氏
この調査の目的は、肺虚肝実証を否定するものではなく、肺虚肝実証は臨床的に病理が複雑であり、肝実証なのか肝虚証なのか迷うことが度々あったことから肝虚寒証として治療した結果、良好なケースが多く見られたことを報告。複雑化する病理観の中、基礎理論の重要性を感じさせられたとまとめた。

「ステロイド皮膚症にまつわる酒皶様皮膚炎の改善例」菊一滋氏
所見時、治療中の実例写真をスクリーン上に映しながら経過を視認し、ドライスキンには腎の津液が深く関与していること、経絡治療がステロイド離脱両方の一翼を担える可能性が示唆されたと結んだ。

「HSPである患者を HSPS-J19尺度を用いて評価した症例」木下立彦氏
HSP(Highly Sensitive Person)とは、感覚刺激や感情刺激に敏感な反応を示す繊細な人の総称で、HSP患者に対して治療前後の評価にHSPの客観的指標である心理尺度HSPS-J19を用いた結果を報告。HSP尺度の数値は、肝虚熱証に治療により減少し、これは血が補われ、潔癖性が正常に機能した結果であるとし、さらにHSP尺度の項目は、肝に関連するものが多いと確認されたと発表した。

「筋力低下を伴う腰痛患者の1症例」阿江邦公氏
本症例から、鍼治療が痛みやしびれの軽減に有効で、特に痛みは早期に、痺れは遅延して軽減したが、筋力低下の改善には、12診、期間は1カ月半では課題が残ったと報告したうえで、長期的な治療効果の評価、症例数の拡大、正確な筋力測定器の導入を今後の課題と展望に挙げた。
閉会式
閉会式では、会旗の返還が行われ、第40回目の節目となる次大会について、小山基氏が次回開催地の代表挨拶にて東京で開催されることを発表した。

講演が行われた会議場の外には、業者展示が行われ、以下の関連業者が出展した。
株式会社ファロス、株式会社山正、株式会社前田豊吉商店、株式会社いっしん、日進医療器株式会社、青木実意商店、株式会社医道の日本、セイリン株式会社、株式会社チュウオー、株式会社B&Sコーポレーション

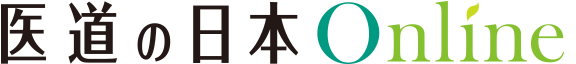
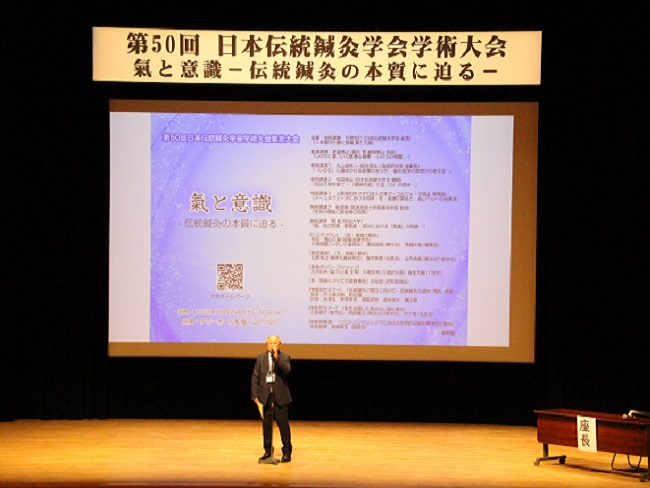







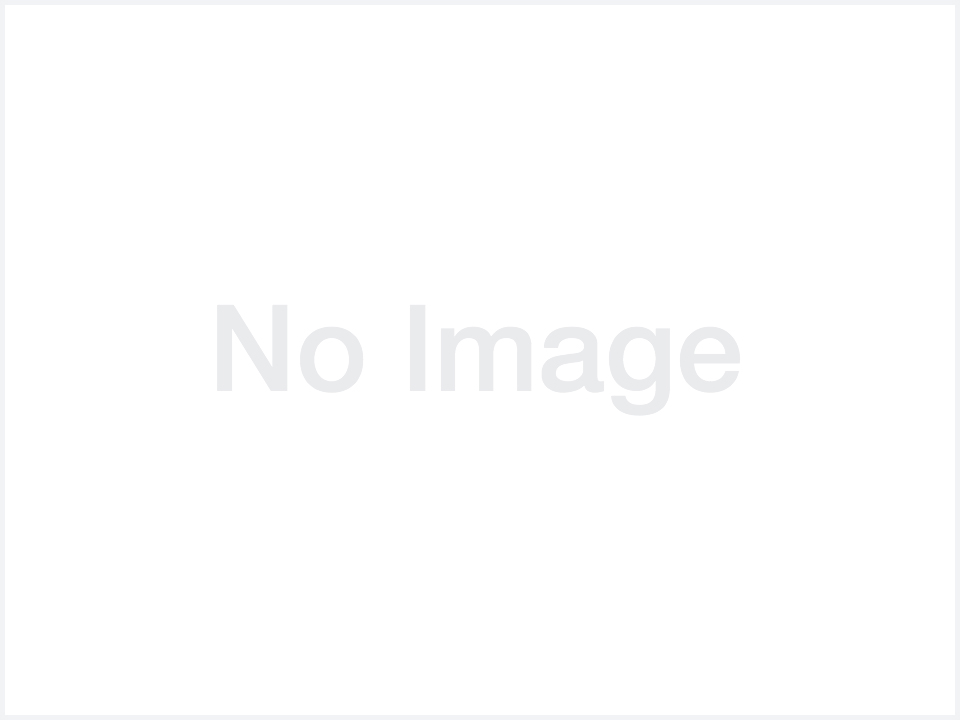

















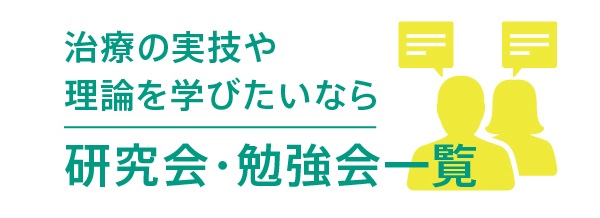
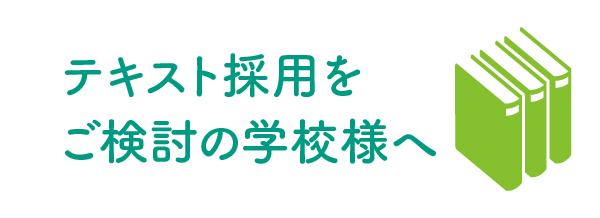
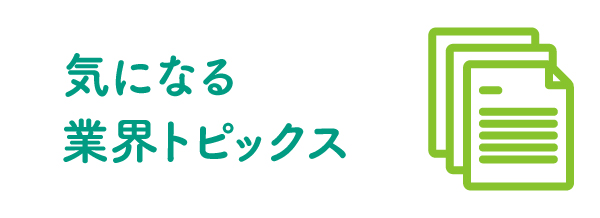
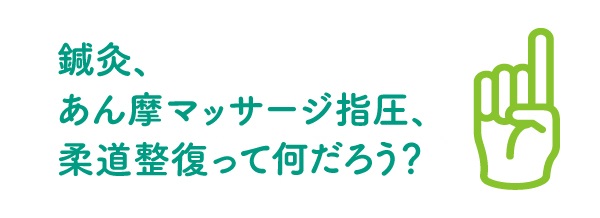


![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)