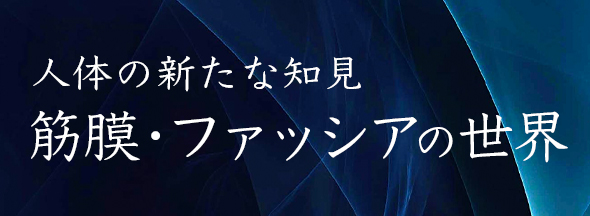鍼灸師にとってのWell-being【第1回】Well-beingという考え方(全3回シリーズ)

はじめに
京都の山間にある鍼灸大学を卒業し、東京の華やいだ街中で修行をさせて頂き、再び京都に戻ったのが25年前。 鍼灸を学ぶ前に通った大学では経営学部に籍を置いていたものの、経営の何たるかを知らずに専門大学へ移ったので、社会の事を知らないまままでの開業となりました。
今思えば、まったく恐ろしい話しですが、「もし廃業することになるならば、それは何かを見落としているか、何かを手抜きしたからだ」と自分に言い聞かせ、21世紀という荒波に漕ぎ出したのでした。
2000年頃から経営コンサルなるものが鍼灸業界にも流行り出し、「肩こりや腰痛といった効果を謳う」や「割引キャンペーン」「チケット制」といった施策が注目されるようになりました。 そういった施策を取り入れれば経営の安定化は早かったのかもしれませんが、「誠意をもって提供する仕事」にそぐわないのではないか、また、「安売り感」が出てしまわないかという印象を持ち、個人的にはそれが嫌で「忍の一字」で何年も過ごしたものです。
とは言うものの悠長な性格のためか、実際には忍耐感や悲壮感はなかったです(笑)。 開業以来お世話になっている会計士の先生曰く、「今だから笑い話しですが、あの数字でよく心が折れませんでしたね」と。
気が付けば開業をしてから随分と時間が経ち、有難いことに多くの方々に来院いただき、また様々な業種からお問い合わせやご依頼を頂けるようになりました。 焦らず、急がす、自分のFeel-goodに従って仕事を積み上げてきた結果として、これまでの波乱はすべて良い想い出になっています。 きっとこれからも、この仕事を人生の中心に置いて過ごしていくことと思います。
この度は『やさしい鍼を打つための本』を上梓して頂いた『医道の日本社』様から、オンライン寄稿の企画にお声掛けを頂きました。 東洋医学に携わる私たちが如何にして人々の健康や幸福に寄与し、それを自分の喜びとして受け取れるのか、全3回のシリーズで読者の皆さんと考えていきたいと考えています。
変わりつつある資本主義
京都というのは興味深い街で、資本金額の大きさや社員数の多さが評価されることがありません。 むしろ「何年やってはんの?」と、その事業の継続年数が評価されることが多い傾向にあるのです。
つまり、腰を据えて街の暮らしと向き合い、ゆっくりと文化を醸成することを企業価値と捉えているのです。 M&Aを繰り返し、短期的に収益を上げることを良しとする現代の経営とは異なる文脈が、1400年続く街の正義なのです。
京都の中心地である四条烏丸から西へ2駅のところにある西院という街に、「佰食屋」という食堂があります。 このお店には、3種類のメニューしかありません。
・「国産牛ステーキ丼」
・「国産牛おろしポン酢ステーキ定食」
・「国産牛100%ハンバーグ定食」
しかも一日限定100食を売り切ったら閉店するという、ちょっと変わった御商売を展開されています。 このお店が全国的に有名になった理由は、もちろん事業の根幹である「美味しさ」にもありますが、「100食を売り切ればみんな幸せだ」という見切りの良さにあります。
・「自分たちは年収が幾らあれば充分なのか?
・食材ロスがない仕入れと提供の分水嶺はどこにあるのか?
・家族と過ごす時間をどれくらい欲しいのか?
お金はあればあるほど事業への投資がスムーズになるし、不慮のリスクに対しての備えにもなります。 しかしながら、不確定な未来に備えるために昼夜を問わずに働いたり、従業員のワークライフバランスに配慮が行き届かなかったりすると、今この瞬間に幸せを感じられなかったりするでしょう。
資本主義とは、個人がもっている資本(技術・商品・労働力など)を自由に売買することで利益を生み出す仕組みに従って生きることをいいます。 本来はただそれだけの意味しかなく、右肩上がりに成長し続けなければならないワケではありません。
スケールメリットを出すことをミッションに掲げている企業は、そうしなければならないビジョンを持っているというだけのことなのです。
このように、世間には身の丈に合った資本主義を実践している企業がどんどん増えています。 鍼灸院のような個人経営で成り立っている手のひらサイズの業態も資本主義の一つであって、世界銀行に勤めていた友人は「Small business but excellent」と評していました。 数字を追いかけて自分に負荷を掛ける労働ではなく、自分の信念に従ってムリなく仕事をすることが、WorkとLifeのバランスが取れた心地よい資本主義なのです。
医療という意味
医療とは、医術・医薬を用いて病気や怪我を治すことを指します。 医療に携わる私たちもそう思っていますし、それを仕事にしています。 しかし長崎でオランダとの交易が始まる江戸末期を迎えるまで、日本に「医療」という言葉はありませんでした。
外科手術を導入するために蘭学(西洋医学)を翻訳するための「蕃書調所」が設置され、文明開化とともに「医療」や「健康」という言葉が生み出されることとなったのです。 福沢諭吉や西周がどのような想いを込めて造語をしたのかは知り得ませんが、歴史的な教養人たちが考え付いたことですから、きっと深い意味が込められているに違いありません。
「漢字を訓読みすると、その意味が分かります」と、小学校の国語で習いました。 きっと「医療」を訓読みしてみれば、この言葉の意味に近付けるかもしれません。
・医=くすし、いやし
・療=いやす
そのどちらもが「癒し」であることに、少し驚きませんか? 「癒」とは、心から辛さを抜き去るという意味ですから、ただ病苦から解放すればよいというものではなく、優しさや慈しみが求められます。 データを分析し適切に処方をしているにも関わらず、医師の診察について患者からのクレームが絶えないのは、そこに癒しが感じられないからではないでしょうか?
何事につけても効率が求められる時代ですが、どうやら医療に求められるのはコストパフォーマンスやタイムパフォーマンスだけではないようです。 自分の心と身体を丁寧に癒すことでしか、満足に足る本当の意味での医療は為しえない。 そのことを、約160年前の偉人たちは見抜いていたように感じます。
果たして私たちは医療人として振る舞い、医療を提供し、その結果として人々を健康へ誘うことができているのでしょうか? 痛みのスケールが軽減されたり、血液データを正常範囲に戻すことは、医療の成果物ではあるけれど、即ちイコールではないということを、明治時代以前から続く伝統医学に携わる者として心に留めておきたいと思います。
・健=すこやか、したたか、たけし
・康=やすい、やすらか
※第57回日本東洋医学会学術総会「明治維新の際、日本の医療体制に何が起こったか」吉良枝郎
WHOという視点
ご案内の通りWHO(World Health Organization)は、肉体的・精神的・社会的に満たされた状態を健康(Well-being)と定義し、「すべての人々が可能な最高の健康水準に到達する」ために、様々な疾患に関する国際的なガイドラインを策定しています。 具体的にはWHO加盟国の医療機関に於いて、国際的に統一された疾病分類(ICD)に則り、疾病の統計や診療記録を行っています。
各国が自国の正義を掛けて戦った第二次世界大戦が終結した約80年前に、疲弊した世界に向けて「Disease=病気・疾患・疲弊」という具体的な課題ではなく、「Health=健康・衛生」という抽象的な概念を提唱した専門機関が作られたということは、とても興味深いことだと思います。
東洋医学的な視点で言い換えるならば、治療ではなく養生、あるいは症状ではなく体質という「ふわっ」としたコンセプトが戦勝国で構成される国連で採択された背景に、ある一人の男性が大きな影響を及ぼしたという事実はあまり知られていません。
清王朝時代末期に天津で生まれた施思明(スーミン・スー)博士は、ケンブリッジ大学にて医学と科学を学び、イギリスでの臨床を経て中華民国へ帰国。 その後は、中国保健省上席研究員に着任し、WHOの設立に奔走しました。
先述の通り、彼は孔子(儒教)や老子(道教)といった先哲によって育まれた文化を出自としていますから、人間の健康を社会医学的な観点や、beingという長い時間軸で見ることができたのでしょう。彼が残したWHO憲章に東洋医学的な文脈を垣間見ることができるのは、このような背景によるものに違いありません。
鍼灸師にとってのWell-being
令和の日本におけるWell-beingは、健康経営という文脈で語られることが多い概念です。 この言葉の背景や真意について深堀りしてみると、東洋医学に携わる私たちが提供している医療サービスの本質に直結していることに気付かされます。
東洋医学の根幹である神仙思想や黄老思想の元となっている老子の提言は、即ち心と身体をムリなく整えた結果として訪れる人生に納得することが大切であり、思い描いた理想や他者の人生と比べる必要はないと説くものです。 もちろん急性期の疾患や外傷への対応も私たちの得意分野ではありますが、「未病治」というコンセプトに基づいた東洋医学はWell-beingそのものであると私は確信をしています。
またこのように、医療行政によって提供されている医療サービスとはまったく異なるスタンスでの選択肢を維持するためには、経営者あるいは施術者である私たち自身もWell-beingでありたいと願っています。 そのために、時として負荷がかかっても回復できるレジリエンスを発揮できるように、自分らしい暮らし方をしたり、心地よく日々の仕事に取り組みたいものです。
※厚生労働省「日本とWHO」
※第115回日本医史学会「WHOによる健康の定義の歴史」津屋喜一郎
執筆

中根 一(なかね・はじめ)
株式会社Fiero 代表取締役
鍼灸Meridian烏丸 代表
明治国際医療大学 客員教授
明治東洋医学院専門学校 非常勤講師
大分医学技術専門学校 非常勤講師
経絡治療学会 理事・関西支部長・夏期大学講師
鍼術丹波流宗家 故・岡田明祐氏、岡田明三氏に師事
全日本鍼灸学会 会員
日本慢性疲労学会 会員
ウェルビーイング学会 会員
日本養生普及協会 会員
地域共創 プロジェクトマネージャー
ラグジュアリーホテル オンコールプロジェクトマネージャー
著述家
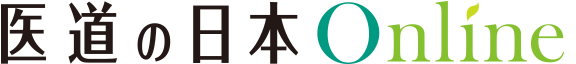
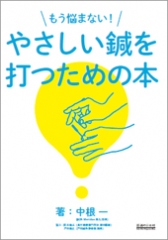
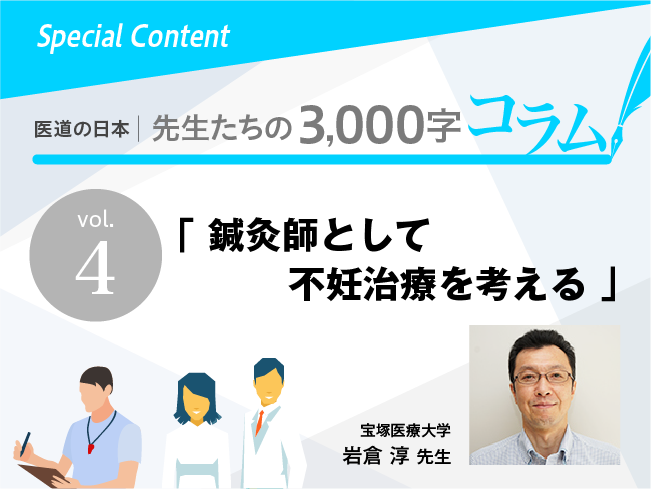

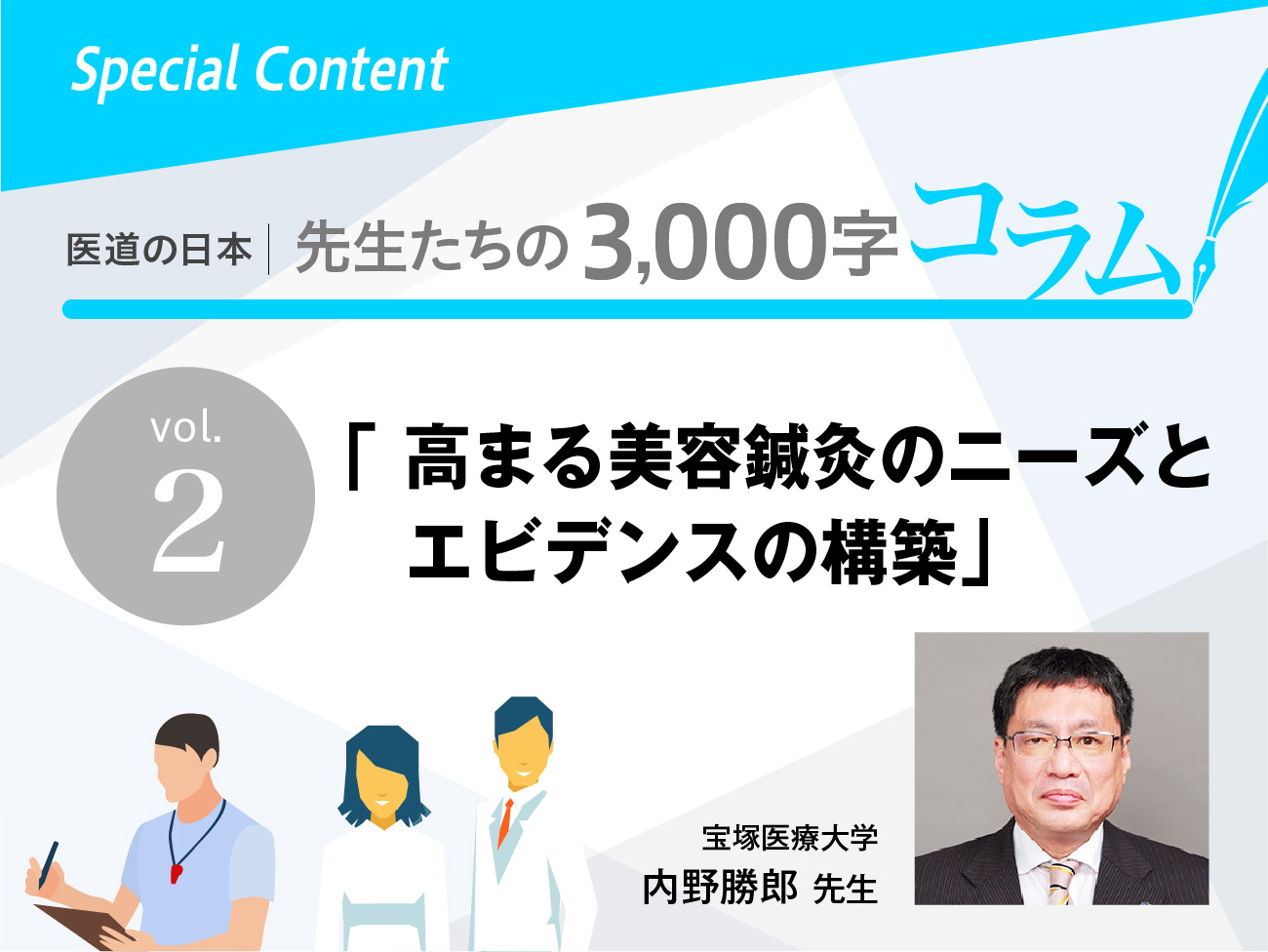
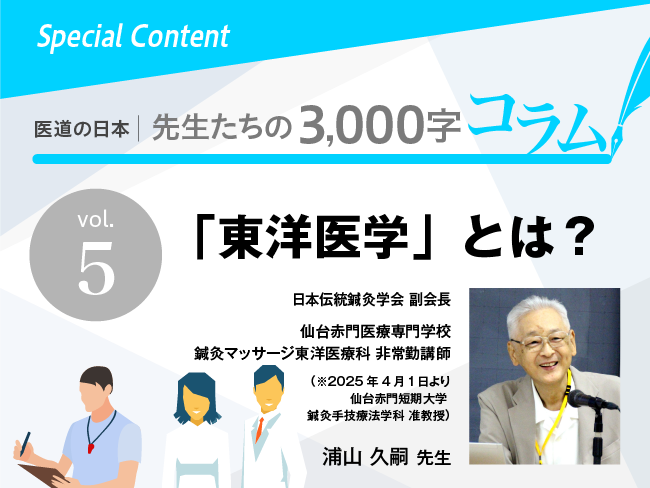


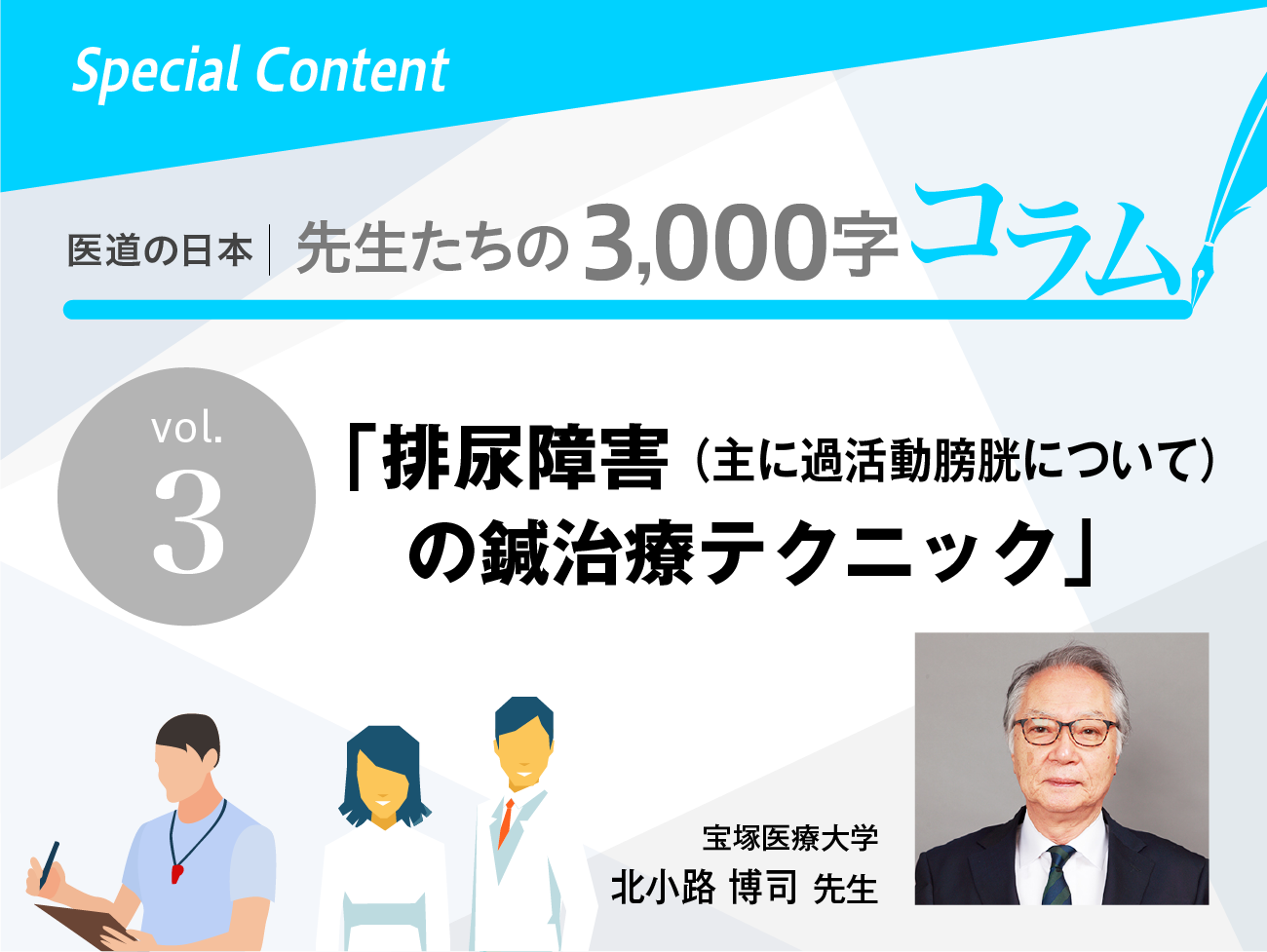
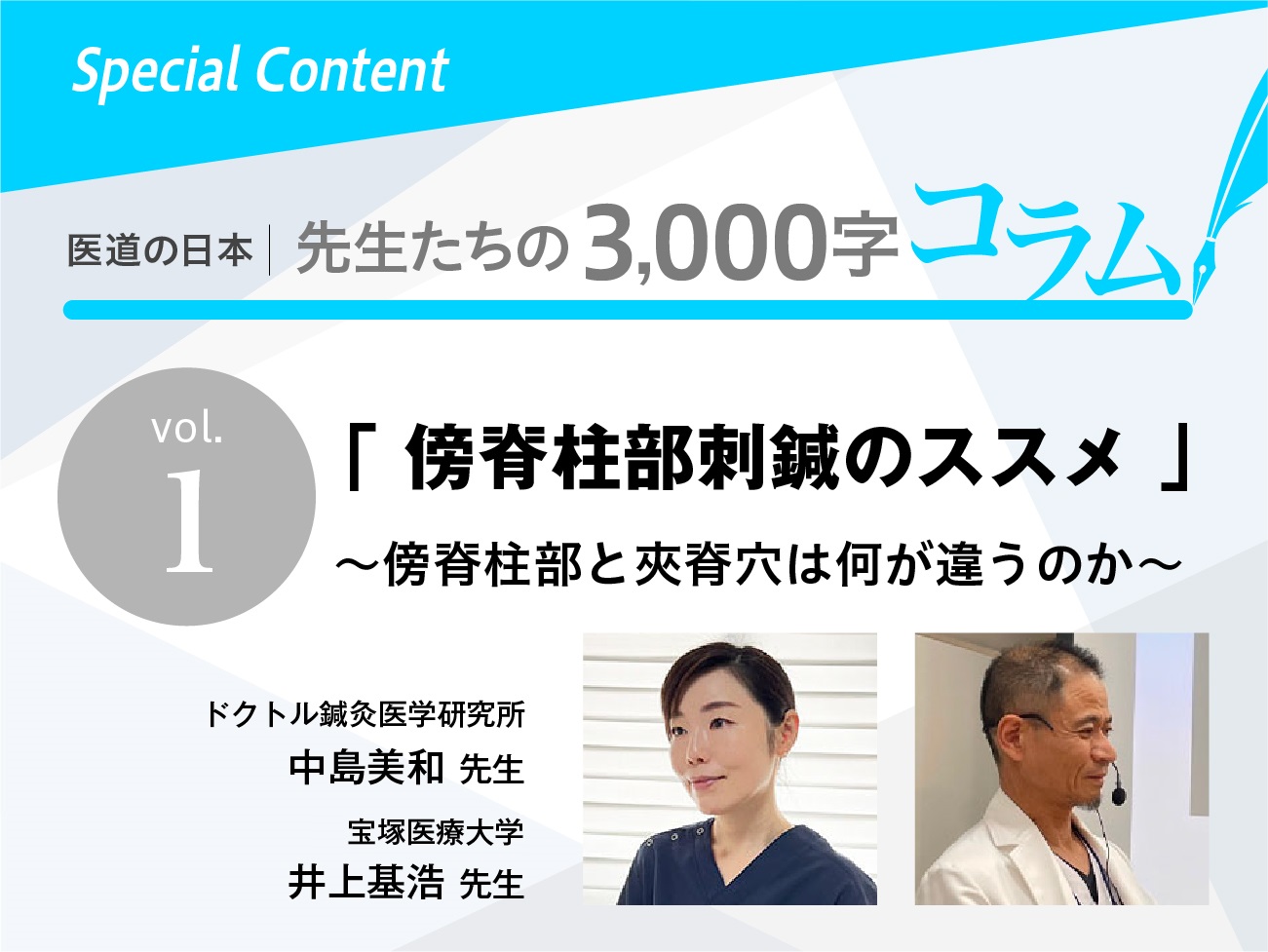


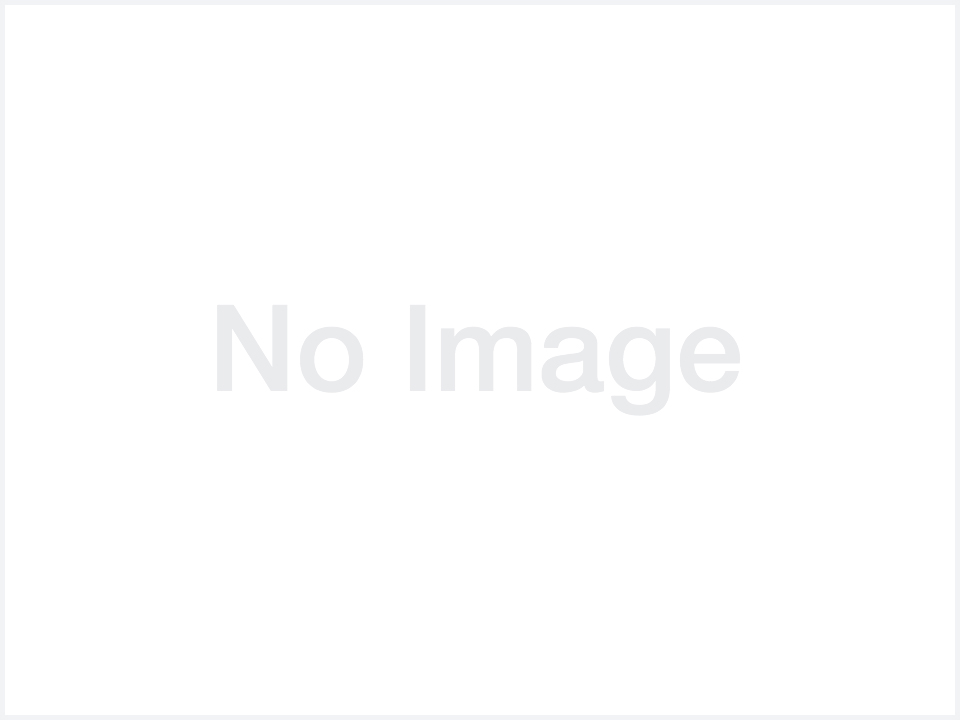




















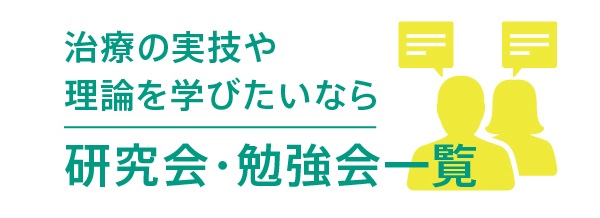
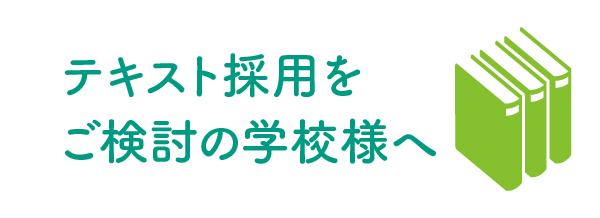
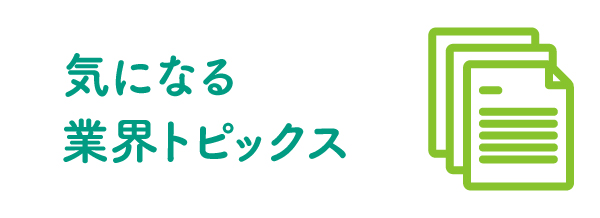
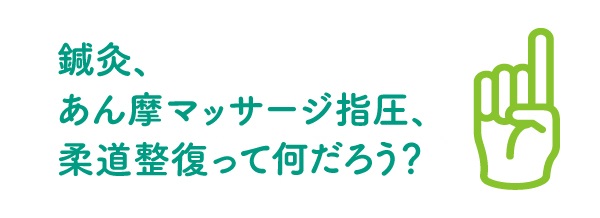

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)